
活用事例サンプル活用事例サンプル活用事例サンプル活用事例サンプル活用事例サンプル活用事例サンプル
- #教育
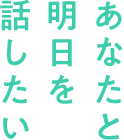
ウェルヴィルは、これまでに培った
「生活に根ざした技術」と、
これからも進化する
「未来を描く技術」を融合させ、
皆様との対話によって
ひとりひとりの豊かな暮らしを実現する
共創パートナーです。
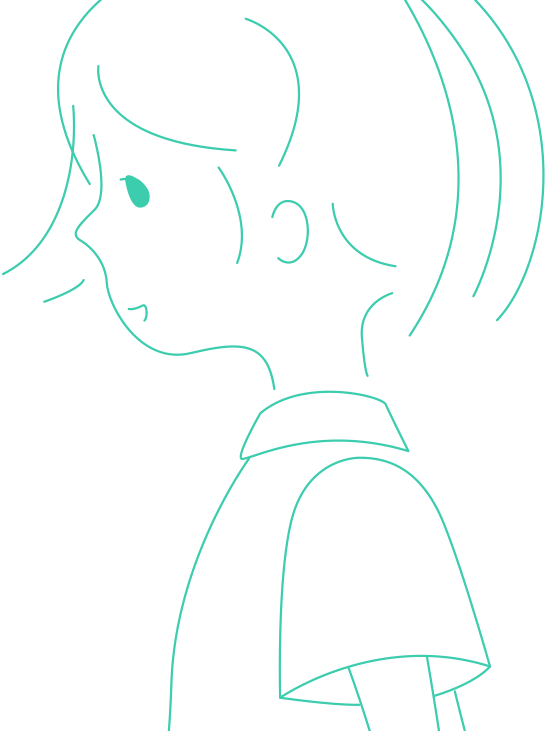

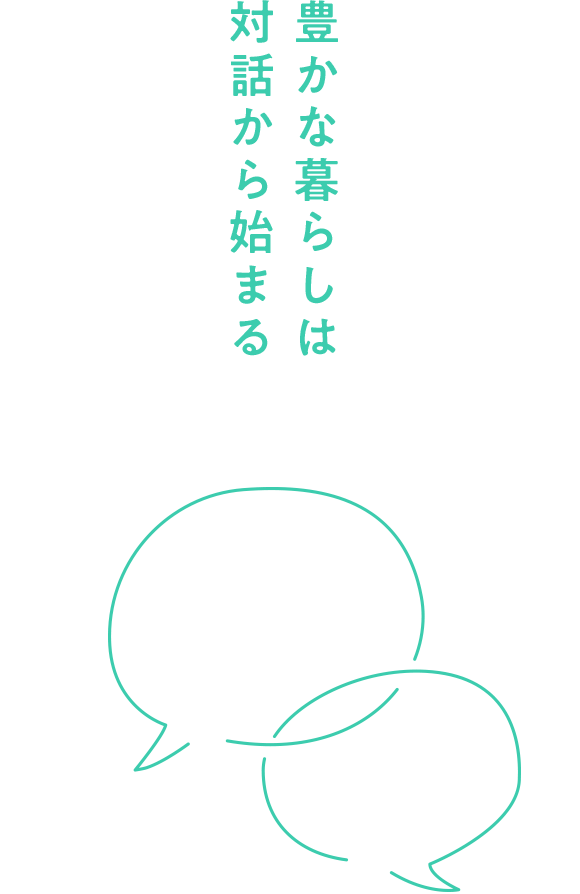
私たちは、テクノロジーでひとりひとりの豊かな暮らしを実現する企業です。
今や生活に欠かせないものとなったテクノロジーですが、これまで足りていなかったものがあります。
それは、“コミュニケーション”です。
日常において、当たり前のように存在するようになったテクノロジーが、目の前の1人にもっと寄り添うことができたら、暮らしはもっと豊かになるはず。
「あなたがいてくれて良かった。」
テクノロジーがそんな存在になれたらどうでしょうか。
一人ひとりの小さな心の動きが、やがて大きな問題すらも解決するかもしれません。
そのために、テクノロジーがこれから始めていかなければならないものは何か。
それが、人との“対話”でした。
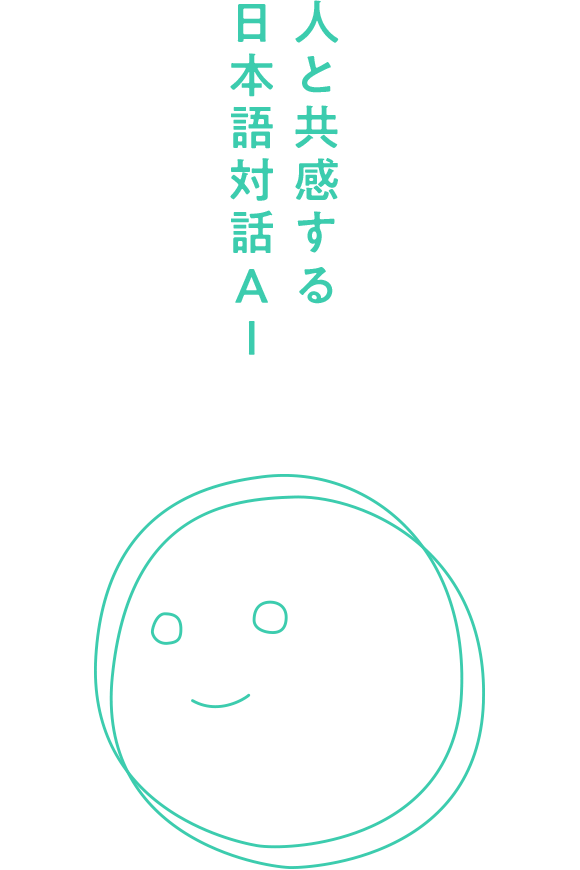
私たちは、心を通わせて向き合う“対話”に注目して研究を開始しました。そこで重要となったのが“共感”です。
「自分のことを
わかろうとしてくれている」
そんな風に感じたとき、人と人は深い対話ができるのだと思います。
ただただ、目の前のひとりを知ろうとする。これこそが、私たちが開発を進めてきた“共感型対話AI”の基本姿勢です。
「うん、大丈夫」
スマートスピーカーのように意味を理解するだけであれば、この言葉を「問題ない」こととして対応するでしょう。
しかし、私たちが開発する対話AIは、この言葉の裏にある寂しさなども感じ取ることができます。
音声も同時に分析する技術で、感情や体調などの人でも気づきにくい変化を捉えることを可能にしているからです。
これはほんの一例ですが、最新技術も培ってきた経験もも、全て同じ目的のために活かされています。
人とAIが共感する暮らしのために―

日本のテクノロジーの描き方の代表に『ドラえもん』があります。
ドラえもんはまるで夢のような道具を沢山持っていますが、そのほとんどがのび太くんに寄り添うことに使われます。
“対話AI”は、子供からお年寄りまで自然扱える身近なテクノロジーとして注目を集めており、これからの暮らしを大きく変えるかもしれません。
だからこそ、私達自身が人に寄り添うテクノロジーの姿を率先して考えています。
事実として、これからのITサービスを創造する日本IT団体連盟の分科会への任命、情報の安心・安全な取り扱いを行うために、内閣府とともに情報銀行の設立・運営にも携わっています。
「私たちが提供しているのは、
いわば“心”です」
どのような状況や姿で人と対話するのかは、一人ひとりに合わせて変化が可能です。
将来そこにいるのは“ネコ型”ではないかもしれませんが、いるだけで安心するような存在であるために、私たちは活動をしています。
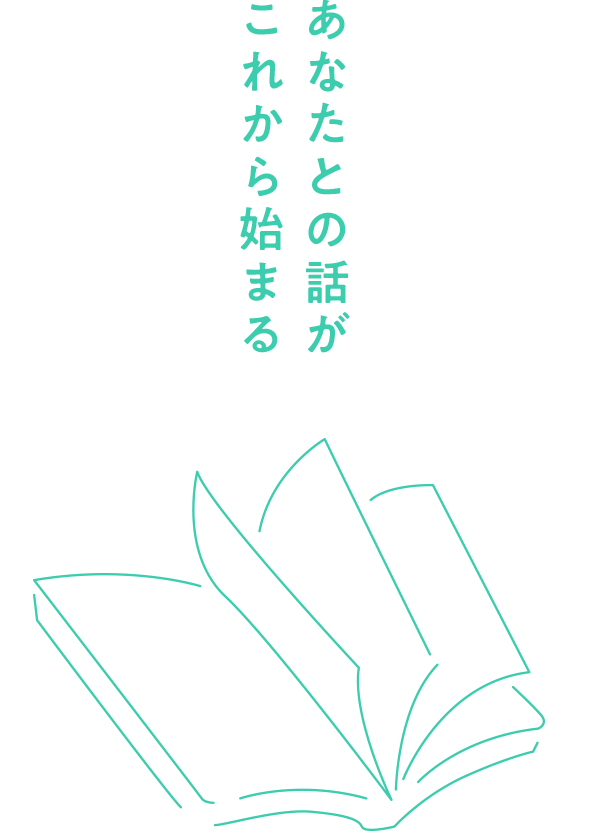
私たちは、様々な方たちと共に話し合いながら、ひとりひとりの豊かな暮らしを実現していくための活動を
「LIFE TALK」
と呼んでいます。そして生み出されたのが、共感型日本語対話AI「LIFE TALK ENGINE」です。
AIとして、人との暮らしの中で、対話ができる存在であること―
企業として、あなたの人生を共に話すことができる存在であること―
そんな想いが込められています。
これから、あなたの豊かな暮らしの話が始まります。
共感型日本語対話AI は、暮らしの中で人と対話することによって、
様々な課題を解決していくことが可能です。こちらではその一例をご紹介しています。
お知らせ
2022.05.03

リード文が入ります。リード文が入ります。リード文が入ります。リード文が入ります。リード文が入ります。リード文が入ります。リード文が入ります。リード文が入ります。リード文が入ります。リード文が入ります。リード文が入ります。リード文が入ります。
プレスリリース
2022.05.09

東急リバブル株式会社とウェルヴィル株式会社は、新築マンション販売における各種物件説明を営業担当者に代わって、お客様と会話しながら説明ができるAIアバターを開発しましたのでお知らせします。
プレスリリース
2021.11.19
株式会社チャーム・ケア・コーポレーションが、ウェルヴィル株式会社に対して出資し、両社は資本提携することとなりましたのでお知らせいたします。両社は、ウェルヴィルの「LIFE TALK ENGINE」を進化させ、将来的に、主に高齢者を対象としたAIヘルスケア関連の次世代サービスの提供に関する事業の検討を進めてまいります。
2022.05.27
テスト
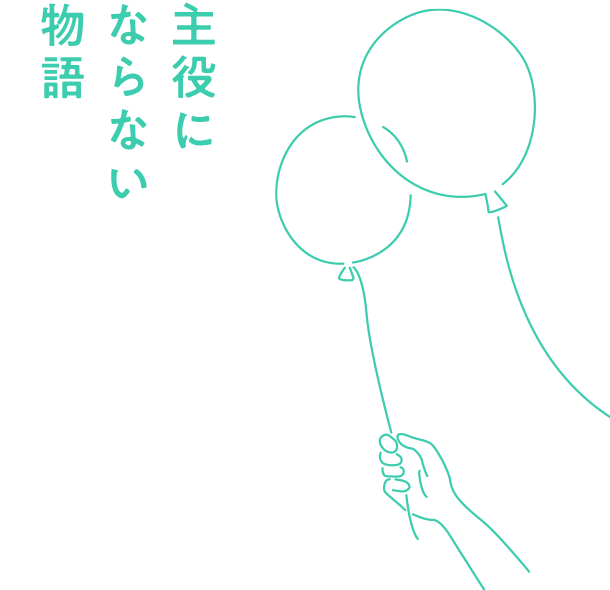
私たちが開発する最先端テクノロジーは
ときにそれ自体が暮らしの中心になってしまうほどの影響力があります。
だからこそ私たちは
“主役にならない”という選択をしました。
テクノロジーが人を変えてしまうのではなく
変わろうとしている人の手助けをするために。
私たちの“主役にならない物語”は
今日も新たな主役を生み出しています。